ポッドキャスト更新 EP.176 国際会議やスモールトークに「自然に入る」質問や参加のこつとは?
Sep 05, 2025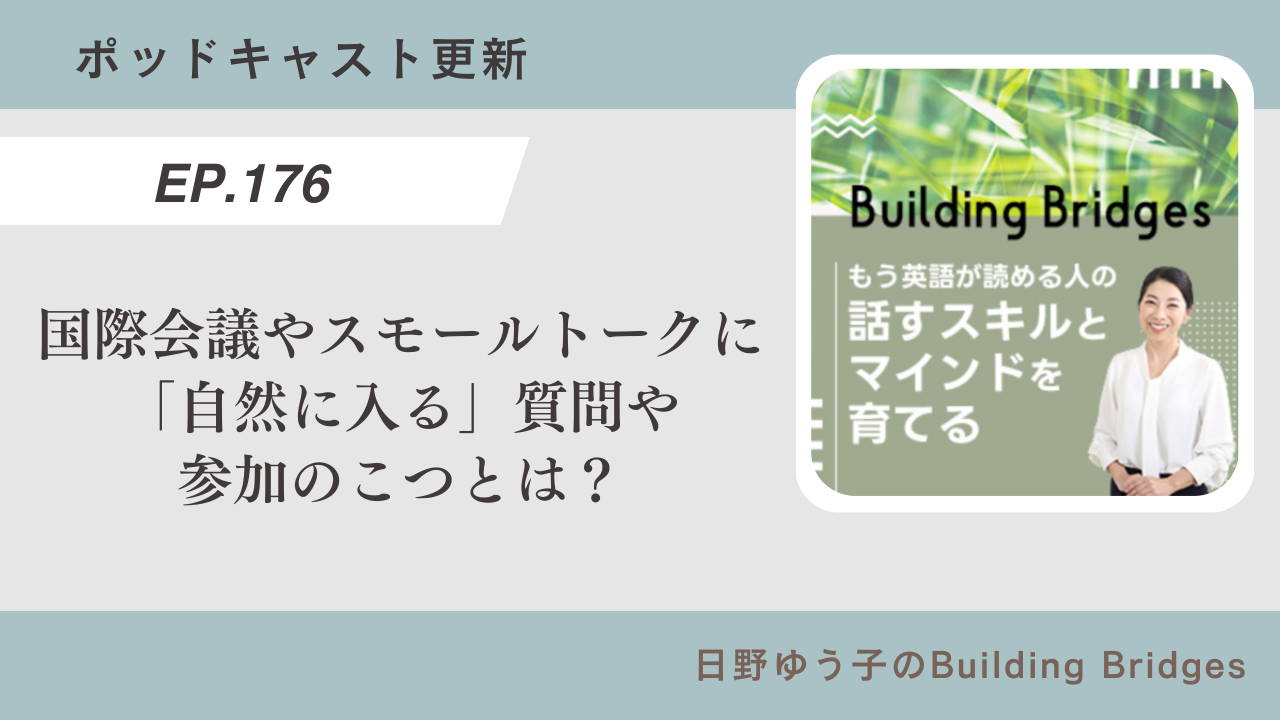
ポッドキャストを更新しました!
こんにちは。スピーキング力養成英語コーチの日野ゆう子です。
今回のPodcastでは、「会議やスモールトークで存在感を出すためにできる工夫とは?」というテーマでお話ししました。
国際的な場で感じる戸惑い
英語力がある方でも「会議で話に入りにくい」「雑談で存在感を出せない」というお悩みをよく伺います。
私自身も、特に欧米の方々と話すときにその絶妙なタイミングで会話に入る力に驚かされることがあります。
自然に「さりげなく入り込む」ことがとても上手なんですよね。
一方で、日本人は「当てられてから発言する」ことに慣れており、自ら会話をリードする経験は少ない傾向があります。
そのため、国際的な場では戸惑いや気後れを感じやすいのです。
背景にある文化の違い
あくまで一般的な話ではあるのですが、欧米の教育では「発言すること」が重視され、小さい頃から意見を述べる練習を積んでいます。
対して日本では授業でも挙手して当てられてから話し出すのが一般的です。
また、沈黙も「よく考えている証拠」と受け取られる文化があります。
そのため、沈黙があっても不安を感じにくいのですが、欧米では「沈黙は避けたいもの」と捉えられることが多いです。
そこからまた「会話を自然につなげる」という行動が発生してきます。
この文化的な背景の違いが、会議や雑談での発言スタイルの差を生んでいるのです。
自分らしく会話に入るコツ
まず大切なのは、うまく会話にはいれないことがあってもそれは欠陥ではなく、「文化が違うから仕方ない」といったん受け入れること。
その上で、自分に合った工夫を見つけていくと安心して会話に参加できます。
私が参考にしているのは「Global Dexterity」という考え方です。
自分の文化や価値観を大切にしつつ、場に合わせて振る舞いを少しずつ調整する方法です。
たとえば私は、発言したいときに軽く手を挙げて「話したいサイン」を示しています。
また、会話に入る前に
「Can I add something here?」
「Can I ask a quick question?」
と一言添えることで、自分も安心でき、相手も聞く準備が整います。
雑談の場でも、ただ笑顔でうなずくだけでは「話したいのに」ともどかしく感じることがありますよね。
そんなときは、話題に対して質問をしたり、自分の経験を少しシェアしてみるのがおすすめです。
ほんの一言を添えるだけで、会話に自然と入りやすくなりますよ。
自分のペースで一歩踏み出すために
今日の内容はあくまで私の工夫の一例です。
大切なのは「あなたに合った方法」を見つけること。
文化の違いがあるのは自然なことです。
それを受け入れた上で、少しずつ自分に合った形で会議や雑談に参加できるようになれば、色々な国の人が集まる場がもっと安心できるものに変わっていきます。
> EP.176 国際会議やスモールトークに「自然に入る」質問や参加のこつとは
\今すぐ聞いてみる/
今日のお話がみなさんの心を少し軽くし、国際的な場での自信につながればとても嬉しいです。
英語を話すスキルと自信「最速」の育て方【限定セミナー】
「いつになったら英語が話せるようになるんだろう…」
英会話が苦手だった元TOEIC講師の私が、かつて何より知っておくべきだったことをギュッと詰め込んだ60分の限定セミナーです。
8割以上の方が変化を実感した、英語を話せる自分への最初の一歩。
この機会にぜひご視聴ください。
オンライン・京都 スピーキング力養成英語コーチング Kyo English Lab
TOEICハイスコア でも英会話が苦手な方へショートカットの英会話力づくりを行っています。
プロフィール 日野ゆう子
英語講師歴計14年のべ3000人に指導経験/上級言語コーチ(国際コーチ連盟認定)/TESOL 英検1級/ 発音指導士/Versant スピーキング70/ Global dexterity practitioner(異文化への適応をサポートしています)
私自身はTOEIC講師→英語をスムーズに楽しく話せるまでに約17年かかてしまった為「効率のよさ」に重きをおいています。

